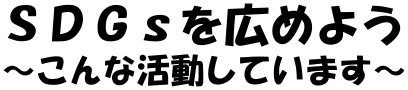「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画~日本各地の湖沼で、こんな取組があります「三方五湖編」~
企画提案者:「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画
(1)三方五湖とは
福井県三方五湖周辺地域は、類い稀なる貴重な地形を持ち、太古から人々が集い文明の起点となった世界に誇れる特別な場所です。美浜町と若狭町に位置する三方湖、水月湖、菅湖、久々子湖、日向湖の5つの湖は繋がっており、豊かな山々から流れ込んだ清らかな川の水はそれぞれの湖を流れて日本海に通じます。同時に、海から入り込む海水によって5つの湖では異なる塩分の濃度を持ち、水質や水深の違いからすべて濃さの違う青色に見えることから「五色の湖」とも呼ばれています。
自然と人が共生する姿のすべてが集約されているといっても過言ではない奇跡の地形のおかげで多様な生態系を有する三方五湖。当たり前に見てきた風景ですが、もう一度その貴重さを考え、この地を訪れてみてください。(三方五湖自然再生協議会HP)
(2)三方五湖自然再生協議会とは(福井県HPから)
三方五湖の自然は、私たちに、食料、農業や漁業、文化など豊かなめぐみをもたらしてきました。ところが近年、豊かだった三方五湖の自然環境は、私たちの気づかない間に急速に損なわれてきています。
そこで、三方五湖周辺流域とその周辺地域において、多様な主体によって自然再生を実現するため、三方五湖自然再生協議会を設立しました。(設立:平成23年5月1日)
※この自然再生協議会は、自然再生推進法に基づく法定協議会で全国で23番目、中部地方では初めての法定協議会です。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/mikata-goko/kyogikai.html
(3)自然再生協議会の6つの取り組み
三方五湖自然再生協議会は6つの部会の活動から形成されています。
6つの部会とは、「自然護岸再生部会」「湖と田んぼのつながり再生部会」「外来生物等対策部会」「環境に優しい農法部会」「環境教育部会」「シジミのなぎさ部会」です。
それぞれの活動の内容は、次からご覧になれます。
(4)「自然再生全体構想」について
平成24年3月に、三方五湖自然再生協議会によって策定された構想で、「はじめに」の項には次のように書かれています。
「三方五湖の自然は、人々に、食料、農業や漁業、文化など豊かなめぐみをもたらしてきました。三方五湖の自然を大切にすることは、すなわち、私たちの生活を豊かに保つことにもつながります。そのためには、三方五湖の自然をもとあった姿に再生する必要があります。 このような背景のもと、行政、地元住民、市民、研究者、各種団体など多様な主体が三方五湖流域とその周辺地域における自然再生を実現するために、三方五湖自然再生協議会を設立しました。この構想は、本協議会の関係者が、湖とそれをとりまく地域の未来のあるべき姿を模索し、実現に向けてのビジョンをとりまとめたものです。」
構想全体については次からご覧になれます。
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/shizen/mikata-goko/kyogikai_d/fil/zentaikousou.pdf
(5)気候変動による三方五湖の淡水生態系等に与える影響調査について
この調査は、気候変動適応情報プラットホームが実施したもので、背景・目的の項に次の記述があります。
「本調査では、将来的な気候変動による影響予測を行い、モニタリング方法や管理方法等の適応策を検討した」。
詳しくは、次から
https://adaptation-platform.nies.go.jp/moej/conso/report/3-3.html
(6)「国連生物多様性の10年日本委員会」による認定について(同委員会HPから)
同委員会による認定連携事業として、次のように紹介されています。
なお次もご覧ください。環境省の新しいサイトです。(環境省HP)
https://policies.env.go.jp/nature/biodiversity/j-gbf/
(7)水月湖の年縞について~7万年分の堆積(福井県HP)
水月湖では1993年、2006年、2012年に年縞(ねんこう)が採取され研究が進められています。水月湖の年縞の長さは45mにもおよび、1年で平均0.7mmという薄さで、7万年という非常に長い年月をかけ途切れなく堆積してできたものです。7万年分もの連続した年縞とその研究成果は国内外から注目されています
水月湖年縞について(解説パネル・ハンドブック) | 福井県ホームページ
(8)ラムサール条約(環境省HPから)
三方五湖は、2005年11月8日に登録されました。環境省HPに次の記載があります。
「三方五湖は、福井県の西岸、若狭湾に面したリアス式海岸にある、タイプが違う大小五つの湖である。・・・五つの湖はすべて水路でつながっているが、それぞれの塩分濃度、面積、水深が異なり、淡水魚、汽水魚、回遊魚など多様な魚類が生息しており、日本固有の魚種も多く見られる。 湖とその周辺は、ヨシ-マコモ群落やヒシ-ヒルムシロ群落を主体とする水生・ 湿性植物群落で構成されている。 水質の違いによって水の色が微妙に違って見えるため、「五色の湖」といわれている。」
詳しくは、次からご覧ください。
この記事のついてのお問い合わせは、
SDGsを広めるサイト「みんなで、大津」運営委員会
E-mail : y.moriguchi3719@gmail.com
まで、お願いいたします。