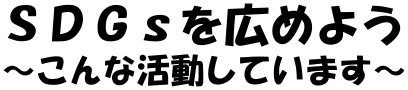「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画~日本各地の湖沼で、こんな取組があります「大沼編」~
企画提案者:「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画
(1)大沼(北海道七飯町)とは
大沼湖沼群は、「七飯町の地質」によると、留の湯溶結疑灰岩が大沼から鹿部にかけて流れていた河川をせき止めて古大沼を形成し、その後駒ヶ岳から流れ下った火山砕屑流堆積物(流れ山泥流)により、古大沼は分断され大沼、小沼、蓴菜沼、婆々沼が形成されたと説明されている。(大沼環境保全計画 別冊資料編「大沼の生い立ち」から)
(2)大沼環境保全計画について(七飯町HPから)
北海道湖沼環境保全基本指針に規定される湖沼環境保全計画に相当する計画で、大沼の環境保全のための各種施策の整合性を確保し、総合的に対策が推進されることを目的に、大沼環境保全対策協議会が策定した計画です。
平成9年(1997年)2月に第1期目の計画を策定し、平成29年(2017年)6月に第3期目の計画を策定しました。
大沼環境保全計画(大沼環境保全対策協議会)
(3)大沼の水質と環境保全(七飯町HPから)
アオコについて、次の記載があります。
大沼では9月~10月にかけて、特に水の流れ(水の対流)の弱い場所において、水面が緑色の粉をまいたような状態になる「アオコ」が発生します。 アオコの正体は、水中の植物プランクトンが大量に増殖したもので、水温や日光、水中に溶けている栄養物質(窒素・リン)などの条件が整うと、植物プランクトン自身の光合成によりどんどん増殖していきます。
水質と対策については詳しくは次から
さらに、大沼の水質改善・水質保全の取り組みは次から
(4)ラムサール条約登録湿地「大沼」(七飯町HPから)
平成24年(2012年)7月3日、ラムサール条約事務局が保管する「国際的に重要な湿地に係る登録簿」に大沼が登録されました。これにより、大沼が「ラムサール条約登録湿地」となりました。
七飯町は、秀峰駒ヶ岳と大沼湖・小沼湖・蓴菜沼を有する風光明媚な大沼国定公園や、仁山高原、横津岳、赤松並木等の自然環境に恵まれております。
詳しくは次から
https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000620.html
(5)大沼の自然と生態系(まるごと大沼HPから)
①水質保全の取り組み
大沼は、自然環境の変化や生活排水などのさまざまな環境要因による有機汚濁や、富栄養化が懸念されています。このままの状能では、せっかくの美しい風景をつぎの世代に残せないのでは…というおそれがあることから、平成7年に北海道の湖沼環境保全基本指針に基づく重点対策湖沼に指定されました。
続きを詳しくは次から。
https://www.onuma-guide.com/natures/onuma-nature/water-quality
②大沼の自然と生態系
大沼を形成する、駒ヶ岳、大沼・小沼・蓴菜沼などの大小の湖沼群、周辺の森や山々には、貴重な自然が残っています。
続きを詳しくは次から。
https://www.onuma-guide.com/natures/onuma-nature
➂湖の生態系~湖とそこにすむ生きものたち~(下記は抜粋)
湖面は、例年12月上旬から翌年4月上旬まで結氷し、4月中旬までに解氷します。春から夏にかけて、湖水は表面から温められますが、温められた水は軽いため、深いところの水と混ざりにくくなります。ちょうどお風呂に入るとき、かき混ぜないと上だけ熱くて下が冷たいのと似ていいます。このような状態を「水柱が成層した」といい、水温の急激に変化する深度を「温度躍層」と呼びます。
湖の富栄養化が進行すると、藻類などによる湖面の着色現象が見られるようになります。これを「水の華」と呼び、構成する植物プランクトンの一つをアオコといいます。
詳しくは次から。
https://www.onuma-guide.com/natures/onuma-nature/lake-ecosystem
(6)特定外来生物について(七飯町HPから)
侵略的外来種による生態系等への被害を防ぐため、2004年に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (外来生物法)」が制定されました。この法律では、海外から日本に導入された生物の中で、特に生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼす、あるいはそのおそれがあるものを「特定外来生物」に指定し、侵入や分布の拡大を防ぐための各種規制を行うとともに、その防除などについて規定しています。
七飯町内で確認した主な特定外来生物 (侵入生物データベース)
詳しくは次から
https://www.town.nanae.hokkaido.jp/hotnews/detail/00016328.html
(7)大沼の自然について(七飯町HPから)
次から大沼の自然の豊かさがご覧になれます。
大沼で観察できるその他の動物(哺乳類・両性類) | 北海道七飯町
(8)湖底の泥から地球環境の変動を読み解く(七飯町HPから)
大沼、小沼、蓴菜沼、2~3の小池沼(ショウチショウ)から成る大沼湖沼群は、寛永17年(1640年)の駒ヶ岳大噴火による噴出物や、山が崩れたために生産された大量の土砂によって、山麓の川がせき止められてできました。
つまり、大沼の湖底堆積物は、下から上へ(過去から現在まで)積み重ねられたものですから、これまでの多様な出来事が記録されている記録紙であると言うことができます。したがって、その堆積物を調べることにより、駒ヶ岳の火山活動や気候変動を解明でき、近年の豪雨や畑地・牧草地の土砂が流入した痕跡も知ることができます。
大沼の湖底の泥から地域環境・地球環境変動を読み解く | 北海道七飯町
(9)北海道ラムサールネットワーク(同HPから)
大沼は2012年7月3日にラムサール条約に登録されました。北海道には大沼の他に12か所がラムサール条約に登録されています。詳しい情報は次から
北海道ラムサールネットワーク Hokkaido Ramsar Network
(10)大沼環境保全対策協議会(AIによる)
大沼環境保全対策協議会は、北海道七飯町にある大沼の水質や自然環境を守るために設立された協議会です。関係機関や地域の団体が連携し、「大沼環境保全計画」に基づいてさまざまな対策を進めています。
設立の背景
- 大沼は1972年に環境基準が設定され、以降水質の監視が続けられてきました。
- 1980年以降、水質基準(特にCOD:化学的酸素要求量)を満たせない状態が続いています。
- 1995年に「重点対策湖沼」に指定され、関係機関による協議会が設置されました。
協議会には以下のような団体が参加しています
- 七飯町、森町、鹿部町(自治体)
- 北海道開発局函館開発建設部、北海道渡島総合振興局(行政機関)
- 大沼漁業協同組合、JA新函館(事業者)
- 七飯大沼国際観光コンベンション協会(観光業)
- 大沼ラムサール協議会(住民団体)
- 環境保全計画の策定と実施
- 下水道や浄化槽の整備
- 緑化推進やアオコ(藻類の異常繁殖)対策
- 水質モニタリングと改善策の検討
この記事についてのお問い合わせは、
SDGsを広めるサイト「みんなで、大津」運営委員会
E-mail : y.moriguchi3719@gmail.com
まで、お願いいたします。