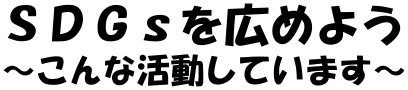「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画~日本各地の湖沼で、こんな取組があります~「沖縄のラムサール条約登録湿地群編」~
企画提案者:「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画
【事務局から】今回は、「沖縄ラムサール条約登録湿地群編」とします。湖沼と湿地とはその概念は少し違うかも知れませんが、琵琶湖をはじめ今回取りあげている湖沼にも「大沼」「尾瀬」「宍道湖・中海」「三方五湖」がラムサール条約に登録されており、湖沼と湿地とは縁が深いと考えます。沖縄には守るべき豊かな自然があります。ここではそれらを紹介します。
(1)湿地とは(環境省HPから)
ラムサール条約では、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水(海水)であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」(条約第1条1)と定義しています。これには、湿原、湖沼、ダム湖、河川、ため池、湧水地、水田、遊水池、地下水系、塩性湿地、マングローブ林、干潟、藻場、サンゴ礁などが含まれます。
詳しくは、次からご覧ください。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/About_RamsarSite.html
(2)沖縄のラムサール条約登録湿地について(沖縄県HPから)
ここに沖縄県のラムサール条約に関する記述があります。
https://www.pref.okinawa.jp/kurashikankyo/shizenseibutsu/1004724/1004726.html
そして、「ラムサール条約の3つの柱とは」として、次のように書かれています。
「条約の目的である、湿地の「保全・再生」と「ワイズユース(賢明な利用)」、そしてこれらを支え、促進する「交流・学習」これが条約の基盤となる3つの考え方です」
1.保全・再生
水鳥の生息地としてだけでなく、私たちの生活環境を支える重要な生態系として、幅広く湿地の保全・再生を呼びかけています。
2.賢明な利用
ラムサール条約では、産業や地域の人々の生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(Wise Use ワイズユース)」を提唱しています。賢明な利用とは、湿地の生態系を維持しつつ、そこから得られる恵みを持続的に活用することです。
3.交流・学習
ラムサール条約では、湿地の保全や賢明な利用のために、人々の交流や情報の交換、教育、普及啓発活動を進めることを決議しています。
(3)沖縄のラムサール条約登録湿地の紹介
沖縄県には5つの登録湿地があります。その5つをご紹介します。(環境省HPから)
①漫湖
1999年5月15日に登録されました。概要から抜粋します。
「かつての漫湖は那覇港の奥に広がる入江であったが、戦後の埋め立てによって河川河口域の地形に変化した。さらに、河川上流部の開発によって流入した土砂が堆積し干潟が形成された。海から3km上流の内陸にあるが、海と同じように潮の干満差の影響を強く受け、満潮時には干潟の大部分が水の中に沈み、・・・漫湖の南岸にはマングローブ林が分布しており、その中に小規模のヨシ原が点在する。干潟は、カニや貝、ゴカイといった底生生物が豊富なほか、汽水域特有の稚魚やハゼ類などの魚類も多く生息し、水鳥にとって貴重な餌資源となっている。地理的にも渡り鳥のルート上に位置する漫湖は、日本列島を縦断するシギ・チドリ類の重要な中継地または越冬地となっている」
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/51_Manko.pdf
②久米島渓流・湿地
2008年10月30日に登録されました。概要から抜粋します。
「久米島は、沖縄島の西約100kmにある面積約5,950ヘクタール、周囲約48kmの島である。・・・自然度の高い森と伏流する清流によって、湿潤で良好な環境が保たれ、キクザトサワヘビやクメジマボタル、クメジマオオサワガニなど絶滅が危惧される多くの久米島固有種が生息する久米島独特の生態系で、学術的価値の高い湿地である」
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/49_Stream_in_Kume-jima.pdf
➂慶良間諸島海域
2005年11月8日に登録されました。概要から抜粋します。
「慶良間諸島は、沖縄本島の西方20~40kmにある渡嘉敷(とかしき)島、座間味(ざまみ)島、阿嘉(あか)島、慶留間(げるま)島など30あまりの小さな島々である。・・・自然度の高い日本でも有数の美しい海域である。世界的にみても希少なサンゴ群を内包する透明度の高い海は「ケラマブルー」と称され、美しい 自然を求め海外からも多くの観光客が訪れている」
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/50_Keramashoto_Coral_Reef.pdf
④与那覇湾
2012年7月3日に登録されました。概要から抜粋します。
「宮古島は、沖縄本島から南西へ約287 km離れた場所に位置し、周囲約131km、面積約1万5,900ヘクタールの、高温多湿な亜熱帯海洋性気候の島である。その宮古島の南西部に位置し、宮古島市平良と下地にまたがっている島内最大の干潟が与那覇湾で・・・沿岸部には干潟を取り巻くようにメヒルギなどのマングローブ林、陸域にはアダン群落、オオハマボウ群落などが占め、また湾口付近にはリュウキュウスガモ、 湿地にかかわる動植物 ベニアマモ、ボウバアマモを主とする広大な海草藻場広がっており、多様な自然環境を有している。与那覇湾では、底生生物、甲殻類、魚類などが豊富であるために、シギ・チドリ類、サギ類などの水鳥にとって欠かせない採餌場や休息場として利用されている」
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/52_Yonaha-wan.pdf
⑤名蔵アンパル
2005年11月8日に登録されました。概要から抜粋します。
「日本列島の南西端に位置する八重山諸島。その中心が石垣島である。・・・ 名蔵アンパルは、石垣島の西岸、名蔵湾に面した名蔵川河口部の、干潟である。亜熱帯地域に見られる典型的な湿地である干潟、マングローブ林、海浜および海岸林などで構成される、多様な自然環境がひとまとまりになった、日本では貴重なタイプの湿地である」
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/53_Nagura-Amparu.pdf
(4)漫湖水鳥・湿地センターの取り組み(同センターHPから)
「漫湖へようこそ」に次のように書かれています。漫湖は干潟です。
「ラムサール条約登録湿地である漫湖。那覇の中心街からほど近い、都会の中にある湿地ですが、水鳥やカニ類など実に様々な生き物が観察できます。鳥類は、101種の水鳥を含むおよそ200種がこれまでに観察されています。この中には、絶滅が心配されるクロツラヘラサギやハヤブサ、セイタカシギ、アカアシシギなどの種が含まれます。秋から冬、春にかけては、シギ・チドリ類が訪れ、100羽を超すハマシギやムナグロの群れが見られることもあります。このような鳥たちの餌となるカニや貝、ゴカイなどの底生生物も豊富です。夏の暑い時期の干潮時、干潟一面を埋め尽くすカニ達の姿は圧巻です」
詳しくは同センターのHPをご覧ください。
https://www.manko-mizudori.net/
この記事のついてのお問い合わせは、
SDGsを広めるサイト「みんなで、大津」運営委員会
E-mail : y.moriguchi3719@gmail.com
まで、お願いいたします。