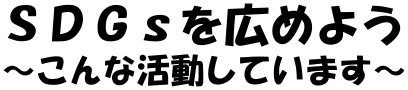「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画~日本各地の湖沼で、こんな取組があります「芦ノ湖編」
企画提案者:「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画
(1)芦ノ湖とは(箱根町HP)
芦ノ湖は、箱根火山の中にあるカルデラ湖(注1)で、標高724mに位置し、周囲19km、面積6.9km2、最深部は43.5mもあります。
芦ノ湖が誕生したのは、今から約3,100年前に起きた神山の水蒸気爆発による土石流が、当時仙石原に流れていた川をせきとめて、その上流に水がたまり、湖になりました。
(注1)カルデラ湖: カルデラとは、火山の活動によってできた大きな凹地のこと。カルデラ湖とは、カルデラ全体または一部に雨水が貯まり湖になったもの。
(原文にあるルビは除きました)
詳しくは、次からご覧になれます。
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000001498/index.html
(2)芦ノ湖に係る水質について(神奈川県HPから)
詳しくは、次のアドレスからご覧ください。
・「神奈川県水質調査年表」は、毎年度の水質測定結果を水域別に掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/b4f/suisitu/nenpyo.html
・「水質の状況」は、水質測定結果全般の情報を掲載しています。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/suisitu/joukyou.html
(3)芦ノ湖の生態系
①芦ノ湖の魚たち(箱根ジオパークの情報)
芦ノ湖には現在ワカサギやオオクチバスなど様々な魚種が生息していますが、明治以降に国内外から移入されたものが多くあります。北米原産のオオクチバスは日本で最初に芦ノ湖へ放流されました。北海道原産でベニザケの陸封型(※5)のヒメマスは、明治42年に十和田湖から移植されたのが最初で、生息の南限と言われています。一方で芦ノ湖にもとから住んでいたウグイは、学名に「ハコネ(トリボロドン・ハコネンシス)」が入っており、芦ノ湖産の標本に基づいて名づけられた学術的に重要な意味をもつ魚です。
(※5)陸封型:生活場所の一部または全てが海にある水生動物が、川や湖にとどまって世代交代している状態をいう。
詳しくは次から。
https://hakone-geopark-app.com/area_hakonevolcanic/ashinoko/
また、箱根ジオパークについてさらに詳しくは次からご覧になれます。
https://www.hakone-geopark.jp/hakonegeopark/
② 芦ノ湖の魚紹介(芦之湖漁業協同組合HP)
ニジマス、ヒメマス(明治42年十和田湖から移植)、ワカサギ、ウグイ(学名:ハコネンシス)などが紹介されています。
詳しくは次から。
https://www.ashinoko-gyokyou.com/fish
➂箱根の植物(箱根町HP)
ハコネバラ、ハコネコメツツジが紹介されています。
詳しい内容は次から。
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000000857/index.html
④ふるさとの仲間たち(箱根町HPから)
このコーナーでは、箱根に住んでいる生きものたちの生態を紹介しています。
写真をクリックすると大きな写真と説明がご覧いただけます。
https://www.town.hakone.kanagawa.jp/www/contents/1100000002227/index.html
(4)未来へとつながる湖(explore-hakoneのHP)
・ワカサギは浅い波打ち際で産卵すべく集まる。そこに網をかけることで、魚は網に沿って進み、ボートそばの集魚網に入る仕掛けになっている。
・芦ノ湖のワカサギは、例年3月から産卵期を迎えるため、芦之湖漁協は3月2日から5月の連休くらいまでの間、毎日ワカサギを捕獲している。前述のように魚を水槽に放したら、まずはスクリーンで覆い、光を遮る。こうすることで、ワカサギたちを落ち着かせ、産卵行動をうながすことができる。そのまま20時間ほどおいとくと、彼らは順次、産卵を行なう。
・「マス類の卵は変化に弱いのですが、ワカサギの卵は違います。彼らはほかの魚に捕食されることが多く、いわば生態系の土台を支える魚だからでしょうか、卵自体が非常に強いんです。その生命力の強さで数を増やして種族を保護し、ひいては芦ノ湖の食物連鎖を支えているのです」
(以上、抜粋)
ワカサギに関する興味ある記述があります。
詳しくは次からご覧になれます。
https://explore-hakone.com/ja/blogs/local-news/ashinoko
(5)NPO法人芦ノ湖発淡水の釣りの未来を考える会の取り組み(同法人HP)
淡水魚の釣りの未来のために、様々な活動(ゴミ拾い・フィールド保全・啓蒙活動・釣り大会)をしています。
「水辺に立ち、風を感じながら自然を楽しむことで、非日常の世界を感じさせてくれる魚釣り。手軽で人々を笑顔にする力がある魚釣りには、長い歴史があり、その奥深さ故に一つの文化として受け継がれてきた。そんな魚釣りの文化を大切にし、様々な活動を通じ、未来へ繋げていくことが私たちの想いです」と書かれています。
詳しくは次から。
この記事のついてのお問い合わせは、
SDGsを広めるサイト「みんなで、大津」運営委員会
E-mail : y.moriguchi3719@gmail.com
まで、お願いいたします。