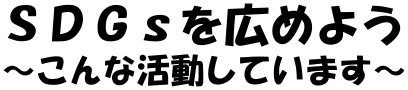「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画~日本各地の湖沼で、こんな取組があります「中禅寺湖・湯ノ湖・奥日光湿原編」~
企画提案者:「びわ湖の日・世界湖沼の日」特別企画
(1)中禅寺湖とは(栃木県HP)
日光の火山が活発に活動していた頃に、男体山の噴火によって出来たせき止め湖である。中禅寺湖の大きさは、東西約6.5キロメートル、南北約1.8キロメートル、周囲約25キロメートル、最大深度163メートル、海抜高度は、1,269メートルで日本一(人造湖を含まない面積4平方キロメートル以上の湖)である。
(すなわち日本で一番高いところにある湖です)
さらに詳しくは、次からご覧ください。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/c05/intro/tochigiken/hakken/shizen3_07.html
(2)中禅寺湖・湯ノ湖の水質(栃木県HP)
①中禅寺湖は面積11.5k㎡、最大水深163mで標高1,269mに位置している天然堰止め湖である。湖水の滞留時間は約6年で、湖沼としては貧栄養湖に属している。湖沼の有機性汚濁の指標(COD(湖心:表層75%値))は2.2mg/ℓ(基準値1mg/ℓ)、全りん(湖心:表層平均値)は0.006mg/ℓ(基準値0.005mg/ℓ)であり、COD及び全りんは環境基準を達成しなかった。過去10年間を見ると水質はほぼ横ばいで推移している。
②湯ノ湖は面積0.35k㎡、最大水深14.5mで標高1,478mに位置している天然堰止め湖である。湖水の滞留時間は約30日で、水深も浅く、富栄養化しやすい湖沼といえる。COD(湖心:全層75%値)は3.3mg/ℓ(基準値3mg/ℓ)、全窒素(湖心:表層平均値)は 0.29mg/ℓ(基準値0.4mg/ℓ)、全りん(湖心:表層平均値)は0.014mg/ℓ(基準値0.03mg/ℓ)であり、CODは環境基準を達成しなかった。過去10年間で見ると水質はほぼ横ばいで推移している。
以上のとおり詳しく書かれています。そして、両湖の水質の推移を示す図が掲載されています。
「令和6(2024)年度環境の状況及び施策に関する報告書」(栃木県環境白書59~60頁から引用)
詳しくは、次からご覧になれます。
https://www.pref.tochigi.lg.jp/d01/eco/kankyou/hozen/documents/r6kankyou_hakusyo.pdf
(3)湯ノ湖・中禅寺湖の水(奥日光清流清湖保全協議会HP)
湯ノ湖は奥日光の最上流部にある「せき止め湖」で、湯川によって下流に位置する中禅寺湖につながっています。
二つの湖の水については、次からご覧ください。
https://www.city.nikko.lg.jp/material/files/group/32/yunokoqa2.pdf
(4)奥日光の自然(環境省日光湯元ビジターセンターの情報)
「奥日光の花々」 http://www.nikkoyumoto-vc.com/nature/flower.html
「奥日光の野鳥」 https://www.toyota-shokki.co.jp/index.html
などが見られます。
(5)奥日光の湿原(日光市HP)
栃木県日光市にある湯ノ湖、湯川、戦場ヶ原、小田代原のうちの、260.41ヘクタールが「奥日光の湿原」として2005年、ラムサール条約湿地に登録されました。それまでは日本の登録湿地は13ヶ所でしたが、今回の登録で一気に20ヶ所が増え、合計33ヶ所になりました。「奥日光の湿原」は全域が日光国立公園に指定されており、自然公園法等によって保全が図られています。われわれは責任を持って湿地とその周辺の水系の保全、あるいはそれらの賢明な利用を進めて行くことを世界に宣言したことになります。
詳しくは次から。
https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/2/1/573.html
(6)ラムサール条約登録(環境省HP)
「奥日光の湿原」は、 2005年11月8日にラムサール条約に登録されました。
詳しくは次から。
https://www.env.go.jp/nature/ramsar/conv/ramsarleaflet/23_Oku-Nikko-shitsugen.pdf
(7)NPO法人Lakeside Storiesの取り組み(同法人HP)
奥日光の歴史ある釣り文化の継承や豊かな自然環境の保全等の活動を通じて、人と魚と自然のフェアな関係性を築き、持続可能なトラウトフィッシングの未来を創造することにより、奥日光の価値を高め、次世代に繋いでいきます。
「2100年も鱒が棲み続けられる湖へ」
https://lakesidestories.jp/#message
https://lakesidestories.jp/#works
この記事のついてのお問い合わせは、
SDGsを広めるサイト「みんなで、大津」運営委員会
E-mail : y.moriguchi3719@gmail.com
まで、お願いいたします。